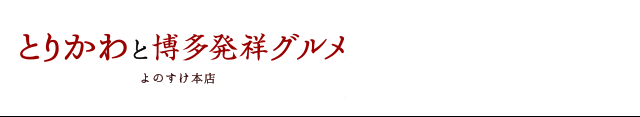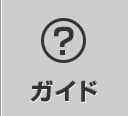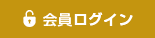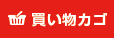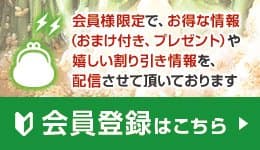もつ鍋の「もつ」とは?
~種類、栄養、選び方~
福岡・博多のもつ鍋に使うもつ、
種類、選び方などについて
福岡・博多のもつ鍋に使うもつ、種類、選び方などについてご紹介したいと思います。
状況は、日々、変化しておりますので、何卒、ご参考程度でお願い申しあげます。
◆ 一般的な「もつ」とは?
鳥獣肉の臓物(ぞうもつ=内臓)のことです。「ホルモン」、畜産副生物、内臓肉とも呼ばれています。もつ=ホルモンですので、どちらも間違いではありません。
中国語では下水。韓国語ではコプチャンなど、また欧米では「バラエティミート」「ファンシーミート」と、呼ばれています。
また、日本では、心臓(ハツ)や舌(タン)などを「赤もつ」 、胃や腸などを「白もつ」と言います。
牛の小腸は、コプチャン、コテッチャン、マルチョウ、シロ、ヒモと呼ばれることもあります。
本来、もつは、食べられる内臓を指しますが、一般的には、小腸・大腸を意味することが多いようです。
◆ 「ホルモン」の由来
特例社団法人日本食肉協議会は、「ホルモン」の語源について、下記のように説明しています。
ホルモンの語源は、大阪弁の捨てるものを意味する「放(ほ)るもん=ホルモン」説や、医学用語であるドイツ語のHormon(ホルモン)、英語のhormoneは、動物体内の組織や器官の活動を調節する生理的物質の総称から、栄養豊富な内臓を食べると、活力がつくとして名付けられた説など諸説あります。ホルモン料理の名称は、戦前から存在し、戦前においては、内臓料理に限らず、スタミナ料理一般、例えば、スッポン料理などもホルモン料理と呼ばれていたことから、「放(ほ)るもん=ホルモン」説は違うと思われます。明治維新の頃の西洋医学(主にドイツ)の影響を受け、栄養豊富で活力がつくとして名付けられた説が、有力・主流であるものと思われます。
◆ 博多もつ鍋の
歴史・起源
福岡・博多においては第二次正解大戦後に、もつ肉とニラをアルミ鍋で醤油味に炊いたものがルーツで、1960年代にはゴマ油で唐辛子を炒め、もつを入れてから味付け用調味料とネギ類を入れてすきやき風に食べられていました。炭鉱で働いていた朝鮮半島の人々が作り始めたものであり、「ホルモン鍋」とも呼ばれています。
◆ 近年の
博多もつ鍋事情
鰹や昆布などでとっただしに醤油や味噌で味付けし、その中に下処理したもつと大量のニラ、キャベツ、にんにく、お好みで唐辛子(鷹の爪)を入れ、火にかけスープで煮込んで食べるスタイルです。もつや野菜を食べ終えた後、残ったスープにちゃんぽん麺を入れて「締め」とするのが一般的です。スープは醤油、味噌が基本ですが、チゲ風、すきやき風等、店舗による個性もあります。牛もつにこだわる店や、水炊き風に酢醤油を付けて食べるスタイルを推奨する店もあります。
ニラやニンニクの強い風味を味わいながら、夏の暑い日に汗をかきながらでも、冬の寒い日に皆でこたつを囲みながらでも、美味しく食べられています。
また、店で提供される際には、一般的に鍋料理で用いられる土鍋はあまり使われず、両側に持ち手の付いた浅いステンレス鍋を使いことが多くみられることも特徴のひとつです。
◆ 福岡・博多の
もつ鍋に使うもつは?
ほとんどのもつ鍋屋が、牛もつを使います。豚もつや鶏もつ等を使うお店は、ほぼ聞いたことがありません。
全国的に見ると、牛肉文化が根強い関西では牛もつ、豚肉文化の関東では豚もつが使われることが多い傾向にあるようです。
栄養面では、牛もつは、豚もつよりもビタミン類が豊富でカロリーが控えめです。
もつ鍋にはもつだけでなく野菜も多く入っています。もつに含まれるコラーゲンと野菜の栄養がたっぷり詰まったもつ鍋は美容や健康にも良い料理です。
地元福岡では、「医者いらず」と言われるほど、もつ鍋には多くの栄養が含まれています。
◆ 美味しい「もつ」の見分け方

私たちがもつ鍋でよく食べているもつは、もつの中でも主に『小腸』と呼ばれている部位です。
もつ特有のコリコリとした歯ざわりと、トロけるような脂が適度についているのが特長です。もつのおいしさは、鮮度で決まると言っても過言ではありません。
腸は普通の赤身の肉と違って筋肉がありません。赤身肉は筋があるため、時間を置き熟成させることで肉が柔らかくなります。しかし、他の肉と違い、腸は筋肉がないため、匂いや腐敗が早く進みます。
ですので、もつは鮮度が命と言えるわけです。肌色や少しピンク色が混ざった色のもつは新鮮です。鮮度が落ちてくると、やや黒くなってきたり、肌色が少し薄くなってきたりします。
また、匂いでも鮮度を判断できます。鮮度が落ちたもつは、酸っぱい匂いがします。
◆ もつの選び方
現在国内で流通しているもつは、主に輸入牛、国産牛、黒毛和牛の3種です。
市場に流通している割合は、5割以上が輸入牛のもつで、次に国産牛、そして黒毛和牛と続きます。
牛も人間と同様、胃がきれいな牛もいれば、病気や荒れている牛もいます。国産牛だからといって、良いもつとは限りません。専門家は、脂の付き具合、脂の感触、色や臭いで美味しいもつを選別します。
店頭で買う時は、見た目の色が大きな判断基準になります。国産牛や黒毛和牛で、ややピンク色、綺麗な白色のもつを選びましょう。茶色や黒っぽい色は、選ばないようにしましょう。
よのすけ本店(良之助本店)では、肉のプロがひとつひとつ選別した、新鮮な国産牛もつを使用しています。
◆ 福岡・博多のもつ鍋の種類は?
まず「小腸もつのみ」「ミックスもつ」の2つに大きく分かれます。
ひとくくりにされている感じのあるもつ鍋ですが、お店によってもつ鍋に使われるもつの種類が異なり、個性があります。
その中でもよく、もつ鍋に使われているもつをご紹介します。
◇ ミックスもつ鍋

よく見かける代表的なミックスもつの種類は、〈小腸〉〈大腸〉〈ハツ〉〈センマイ〉〈ギアラ〉〈ハチノス〉等です。
これらのもつの中から、各お店が独自に選んでいます。また、配合割合もお店によって異なります。
よのすけ本店(良之助本店)では、脂身が美味しい小腸、焼肉でも人気のミノ(牛の第一胃)、ビタミンが豊富で肉感があり、焼き鳥でもお馴染みのハツ(心臓)を均等に使用しています。
歯ごたえのあるしっかりとしたもつを使用するため、様々な食感を楽しめます。また、小腸もつ鍋に比べ、脂身が少ない分、スープ本来の味を楽しむ事が出来ます。
◇ 小腸もつ鍋

脂身がしっかり付いた小腸もつのみを使用したもつ鍋です。
小腸もつは、博多もつ鍋に欠かせない部位です。脂身が付いていて、柔らかく食べやすい部位です。口どけが良く、ぷるぷるの食感と溢れる旨味が特徴です。
よのすけ本店(良之助本店)では、甘みと旨みが凝縮した脂身が豊富な小腸もつを使用しています。さらに、職人が丁寧に仕込むため、臭みがなくふわふわの食感を味わえます。小腸の脂と野菜の旨みが溶け出したスープは絶品です。
◇ スープ
もつ鍋にはもつ鍋に合うスープが必ず必要です。
各店がもつ肉の次に力を入れているのがスープです。スープがその店の味の決め手となります。
いくら良いもつを使用しても、スープに合わなければ台無しです。スープがもつや野菜の味を引き立て、その味が、各店の個性となります。
福岡・博多では「醤油」が最もポピュラーですが、珍しい、チゲや味噌、塩など最近は種類も豊富になってきています。
よのすけ本店(良之助本店)、実店舗では優しさとあっさり味を追求した醤油、濃厚な深みのある味噌、体の芯から温まるチゲの3種類をご用意しています。
◆ もつ鍋 雑学①
平成元年頃までは、ミックスもつを出すお店ばかりで、小腸もつを使ったもつ鍋の方が珍しかったようです。
歯ごたえのしっかりしている「ミックスもつ」に比べ、脂が付いて、ジューシーな「小腸もつ」を使ったもつ鍋が、最近では、多くなっているようです。「ミックスもつ鍋」が主流だった頃から、「やま中」さんでは珍しい「小腸もつ鍋」を提供していました。
今人気である「小腸もつ」をいち早く提供していたこと、もちろんスープも美味しいことで、福岡では、大変有名な人気店になっています。
◆ もつ鍋 雑学②

なぜ、ミックスもつが出回ったのでしょうか?
性能の良い冷凍設備がない昔の時代の事情により、もつは冷蔵状態で、取り引きされていました。
劣化の早いもつを、劣化させる前に早く取り引きしないといけない為、「ミックスもつ」が主流となりました。
まず牛は、食肉センターでさばかれます。そのさばいたもつを、卸会社が買いつけます。この際、牛一頭分のもつが、1単位(1取引き)となります。これを卸会社が、各お店に売ります。
買う方のお店は、ミノだけ買いたいなどの希望があったりしますが、卸会社の売る方は、ハツだけ売れ残っても困る、センマイだけ売れ残っても困るということになります。卸会社は、買いつけた牛一頭分のもつを残らず売り切りたいのです。
それにより、もつは、牛1頭単位で取り引きされるようになりました。
もつが、市場に出回り始めた昔からの主流となっている取り引き形態です。
お店は、牛1頭分のもつを仕入れなければならない為、様々なもつを食べやすいサイズに切り、混ぜあわて使うことになるのです。
この取り引き事情により、もつ鍋に使うもつは、「ミックスもつ」が主流となり、現在でもほぼ変わっていません。
これによって、焼き肉屋やもつ鍋屋で見かけるメニューが、レバー刺し(現在は、提供出来ません)、テールの塩焼き、テールスープ、タン焼き等の似たようなメニューになるのです。
後に、冷凍技術の進化によって比較的保存はしやすくなりましたが、長期保存には向きません。そのためミックスもつ鍋を提供するお店は、まだまだ後を絶ちません。ミックスもつ鍋は、昔ながらの味として、今も福岡県民に親しまれています。
◆ もつの栄養素
牛もつには、重要な栄養素が多く含まれています。他にも、ミネラルや必須アミノ酸といった体に良い栄養素が沢山含まれています。
ロースやバラ等の精肉に比べ、ビタミン類を多く含むことも特徴です。
ホルモン系・内臓肉の栄養価は高く、免疫力や皮膚粘膜の健康に役立つビタミンAや疲労回復への効果があるB群、鉄分(ヘム鉄)や亜鉛等のミネラルも豊富です。
特にアミノ酸は血流をよくする働きもあります。
体温があがるという事は、エネルギー生産が高くなることをいい、持続することで脂肪燃焼などにつながります。
そして、よく咀嚼をする事で、少量でも満腹感が得られ、脳の活性なども促されます。
さらに、ローカロリーです。しっかり下処理されたもつであれば、健康効果、美容効果を望めると言えるでしょう。
また、お肌のプルプル感を保つ為に大切なコラーゲンもたっぷり含まれています。コラーゲンは肌に含まれる成分で、肌の水分保持と若々しさを保つ効果がありますが、加齢とともに減少していきます。化粧品等で外から補うのも良いですが、コラーゲンを含む食品を食べることも健康的な肌を保つためには重要です。
コラーゲンは、摂取しても体内に吸収されにくいと言われています。コラーゲンが効率よく体内で働くためには、アミノ酸やビタミンCを同時に摂取することが必要です。ニラやキャベツ等の野菜と一緒に食べる事で効率よくコラーゲンを身体に取り入れる事が出来ます。もつ鍋は、いつまでも若々しい肌を保ちたいと思う女性の強い味方です。
一方で、プリン体も含まれています。プリン体とは痛風の原因になる成分ですので、過剰摂取は控えましょう。
痛風の原因は、遺伝的要因や生活習慣要因など様々ですが、プリン体を含む食品を一度に過剰に食べすぎてしまうと、こうした病になる可能性もあります。何でもそうですが、体に良いからと言って、同じ食品ばかりを過剰に食べ続けることは危険です。様々な食品をバランスよく摂取することを、日々心がけましょう。
◆ 女性こそ、もつ鍋を
もつの脂肪はコラーゲンの塊です。コラーゲンにはビタミン、ミネラルが含まれ、主に疲労回復効果、美肌効果等があります。
もつ鍋は、高たんぱく低カロリーでビタミンを多く含む栄養豊富な料理です。
美味しいスープで、野菜をたっぷりと食べられるうえ、コラーゲンも豊富なので、美容や健康に関心の強い女性には外せない一品と言えます。
もつはビタミンB1が豊富です。そして、もつ鍋に必ず入っているキャベツには、コラーゲン生成に必要なビタミンCが多く含まれています。もつとキャベツは最強コンビなのです。
もつや野菜から、様々な栄養をたっぷり摂取できる料理なので、福岡・博多では、別名「医者いらず」と呼ばれています。
次のようにもつ肉には違いや特徴がたくさんあります。
お客様には、もつを選ぶ楽しみがあります。
色々な「もつ」を試して、好きなもつを探してみてはいかがですか?
もつ鍋は決まった肉を入れるというルールはないため、それぞれお好きなもつを入れて、「オリジナルもつ鍋」を作るのも楽しいですね。(もつの種類によってはお鍋に合わない場合もあります)
◆ 一般的な牛もつの種類
小腸もつ朝鮮語では、コプチャン、ソチャン、コテッチャン等と呼ばれています。脂身があり、口どけの良さやぷりぷりの食感が特徴です。柔らかいので、小さなお子様や年配の方も食べやすい部位です。
焼肉店でも人気の部位ですが、煮込み料理や串焼きなどにも使われます。
特に小腸をひっくり返した丸腸は、その加工技術の難しさから、九州ホルモンの代表格で人気も高いです。(しかし、ぶつ切りの丸腸は内側が開いてある小腸に比べ、中身が洗いにくいため、小腸の方が衛生的とも言えます。
焼肉ではテッチャンなどと呼ばれています。一頭から2~3kgほどしかとれない貴重部位です。
シマシマ模様が小腸との違いで、小腸にはないシャキシャキ、コリコリの食感が特徴です。
赤身の脂とは違いあっさりしていますし、焼く時に自分の好みで脂の残し方を調節できるので、あまり胃もたれしません。
小腸と同等か、それ以上の人気となっています。本来「トンチャン」も同義語でしたが、最近では豚ホルモンや豚焼肉を「トンチャン焼」と呼んでいる店もあります。西日本では比的脂を多く残し、東日本では綺麗に取り除く傾向があります。
心臓、ハートという意味からついた名称で、他にも心(こころ)とも呼ばれています。
脂身が少なめで旨みが強く、こりこりとした食感が特徴です。ビタミンB1が多く含まれており、消化の手助けを行ってくれます。
臭みもほとんどない為、ホルモンが苦手な方でも食べやすい部位です。
開いた様子が蓑に似ていることからこの名称になりました。
歯ごたえのある食感と淡白な味わいが特徴です。ビタミンB2や亜鉛が多く含まれています。
包丁で切り込みが入れ、硬いミノも食べやすくなっている事が多いです。
朝鮮語の千枚と同意味である千葉(チョニョブ)をそのまま日本語に訳し、今の名称となりました。
たんぱく質含有量が和牛ばら肉と同程度で、脂質がほとんどなく低カロリーなので、さっぱりした味です。
鉄分豊富なことから特に女性に人気な部位です。コレステロールも和牛ばら肉と同程度でホルモンとしては少なく、ダイエットに適した部位です。
博多のもつ鍋屋では、ミックスホルモンの具材の一つとして人気が高いですが、見た目のグロテスクさから苦手な人もいます。表面の灰色の部分を湯むきして「白センマイ」で提供される場合もあります。湯むきは比較的高級店に多いようです。
タンパク質、ビタミンA・B1・B2、鉄分が豊富で栄養価が高い部位です。血の味がすることや、火を通し過ぎるとパサパサな食感になることなど、癖が強く、食べにくいと思われがちですが、繊維はなく柔らかい肉なため、焼肉屋で人気のある部位です。
◆ その他の牛もつの種類
タン(舌)タンは、英語で舌を意味する「tongue」の音に由来しています。他の肉に比べて脂肪分が少ないのが特徴です。牛タンにはタンパク質や鉄分をはじめ、タウリン(アミノ酸の一種)など体づくりに欠かせない栄養素が豊富に含まれています。
最も柔らかい根元部は「上タン」として使われ、舌先になるほど脂肪が多くなると同時に肉も硬くなります。普段外に出ている部分と根本の部分でかなり見た目も違います。刺身で食べるのは根元、焼くのは先の部分が多いようです。
地域によって呼び方が異なります。(ツラミ・頭肉など)よく動かす部分なのでとても濃厚な味と歯応えが特徴です。またタンに似た独特の風味も特徴です。
煮込み料理やシチューによく使われます。赤ワインで煮込む事で独特の風味を消す料理もあります。フランスの伝統的な料理の1つである、ブフ・ブルギニヨンが有名です。
すきみ、ネクタイとも呼ばれています。開いて切れ目を入れている事が多く、クセがあまりない、赤身のような味でホルモンっぽくないのが特徴です。ランプに近い場所にある細長い肉もネクタイと呼びますが、こちらはその形状からそう呼ばれています
語源はsweetbreadが日本語訛りになったものです。
柔らかいが脂っぽさは少なく、フォアグラや白子のようなまったりとしたクリ
ーミィーな食感が特徴です。
特に子牛のものは珍重され‘リードフォー’と呼ばれます。
ちなみに甲状腺・扁桃腺の部分はシビレに含まれないそうです。
ホルモンの中でも最も硬く、切り込みを入れて食べやすくしたものを焼肉にすることが多い部位です。
コリコリとした食感が特徴ですが、味はなく食感を楽しむだけなので、ホルモンの中ではあまり有名ではありません。
ハツモト(心臓に近い動脈)
タケノコ・コリコリなどとも呼ばれます。脂が多く、軟骨のようなコリコリとした食感が特徴です。
塩よりもタレの方が、相性が良く、お肉からも濃い味がします。
一部地方では「嫁泣かせ」とも呼ばれています。動脈は固いのですが、表面が脂でぬるついて、下処理が大変なことからこのように呼ばれているそうです。
横隔膜(ハラミ)からぶら下がっているのでサガリと呼ばれています。非常に柔らかく、ジューシーなのが特徴の部位です。ハラミに比べると若干、脂の量が少なく、あっさりしています。
知らずに食べれば、普通の牛肉と間違えるほどの味と食感ですが、立派なホルモンの仲間です。
焼肉屋さんで定番の部位です。
サガリの周りにつく肉で、旨みが濃厚なのが特徴です。脂がのっており肉に近い味わいのため人気が高いです。
サガリ同様のお肉のようですが、ホルモンの一部として扱われており、スジホルモンとして出す焼肉屋さんもあります。赤身に見えますが内臓肉なので、ローカロリーで、ロースなどに比べてもサシが少なくヘルシーです。
豚の腎臓が空豆の形をしているところから付いた名前ですが、牛の腎臓はブドウ状の形をしています。あまりクセのない味が特徴です。
日本ではほとんど出回っていませんが、ソテーにして食べる国もあります。ちなみに、すき焼きなどで使う牛脂はマメの周りについているもので、ケンネと呼ばれています。
見た目がハチノス状に6角形の網目になっていることからこの名称になりました。独特の風味と歯応えのあるのが特徴です。コラーゲンが豊富に含まれており、あっさりしていて食べやすいのですが、日本ではそれほどメジャーな部位ではないようです。
イタリア料理では煮込み料理「トリッパ」として、パンやパニーニに挟んで食べたりするなど、海外ではよく使われている部位です。
赤センマイとも言われています。英語名abomasumからアボミとも呼ばれます。歯応えがあり、噛めば噛むほど味が出てくるのが特徴です。
小腸だけのもつ鍋に入れると、より味に深みがでて、脂っこさがなくなる為、あっさりとコクのあるもつ鍋に仕上がります。煮込み料理などにも使われます。
胃液を分泌し、生物学的にみる本来の胃の役割を果たす唯一の胃で、残りの3つは食道が進化したものだそうです。
終戦後、基地などで働いていた在日の方が、報酬の代わりにホルモンを貰っていたことから、「ギャラ」が訛ってギアラになったという説が語源と言われています。(諸説あり)
前腹の皮と脂身の間にある赤いスジ肉です。濃厚な肉の旨味です。やや堅めなので、煮込みやボイルで食べたりもします。生を焼いて食べる場合は、薄目にさばきますので、焼き過ぎに注意が必要です。
クセがなくコリコリした歯切れのいい食感が特徴です。
焼くと少し柔らかくなります。高たんぱく質で低カロリーとダイエットにもお勧めです。
開いた形が似ている為この名称になりました。
筋肉が発達している部位なので旨み脂肪が少なく、肉厚で独特な歯応えが特徴です。
小さくカットして使用しますが、下調理でじっくり煮込むことで柔らかく、クセのない味になります。高級もつ鍋屋さんで酢もつの材料として利用されています。
スジとも呼ばれます。
骨粗しょう症などの骨のトラブル防止に効果のあるビタミンKや、肩こりや腰痛に効果のあるビタミンB12などが含まれます。そのままでは硬く、下調理に時間が掛かりますが、コラーゲンがたっぷりな部位です。
いわゆるテールスープに使われている部位です。お尻の部分はヒップとも呼ばれています。コラーゲンが豊富に含まれているので女性に人気な部位です。
スープにしたり、塩・ブラックペッパーを振ってオーブンで焼いたり、濃い目の煮汁でサッと甘辛く煮詰めるなど、様々な調理方法があります。よく煮込んで骨髄の部分がゼラチン状になると、さらに美味しくなります。
もつ鍋発展会主催 ご挨拶
もつ鍋は、博多の郷土料理ですので、誠実に大切に営業しております。
歴史、文化の正しい情報発信や、関係業者さんとの勉強会を開催し、お客様に喜んで頂けます様に、よりよい発展に努めております。
他県の会社さん等も、もつ鍋の通信販売をされていますが、よろしければ、福岡・博多で営業しているもつ鍋屋さんでの通信販売を、是非、お楽しみくださいませ。
福岡・博多のいろんなもつ鍋屋さんの工夫・個性が、お楽しみ頂けますと大変嬉しい限りです。
(よのすけ本店 所在地:福岡市東区香住ヶ丘2-26-24)
もつ鍋の発祥・歴史には、諸説、御座いますので、何卒、ご参考程度でお願い申しあげます。
創業者 謹白
■ 転載について ■
・当ホームページの文章・画像などの内容の無断転載、及び複製などの行為は、ご遠慮ください。・当ホームページに掲載されている全ての画像・文章・情報などは、著作権により保護されております。
・著作権者の許可なくこのサイトの内容の全て、又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写などをすることを固く禁じます。